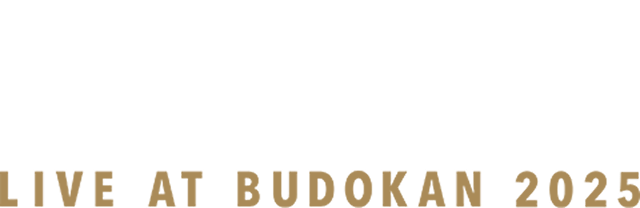LIVE REPORT
初日4/14(月)公演のライブレポート到着!
第2弾は天辰保文さんです!

2025年4月14日、2週間ほど前に誕生日を迎えたエリック・クラプトンが、おそらく80才になって初めてのコンサートで、それも満員の武道館で演奏する最初の曲に選んだのは、「White Room」だった。日本で演奏するのは、2003年の日本ツアー以来なので22年ぶりということになる。このオープニングだけでも、驚きと喜びの交じった歓声で会場は湧いた。1960年代のサイケデリック・ロック・シーンを彩ったワイルドなギター・サウンド、絞り出すような力強いエリックの歌声、そこにケイティ・キスーンとシャロン・ホワイトの二人の女性コーラスが寄り添いながら会場を満たしていく。その後は、再びクリーム時代の「Sunshine Of Your Love」まで一息も入れずに、エレクトリック・セットが続く。そして、MCをはさんでアコースティック・セットへ。ちなみに、MCで語られたのは、一昨年他界されたウドー音楽事務所の創業者、有働誠次郎氏への感謝の思いだった。大切な友人で、正しい道を示してくれた恩師でもある彼のために、今年は何が何でも日本に来ると決めていた、と。
「Kind Hearted Woman Blues」で始まるアコースティック・セットでは、新作『Meanwhile』からの「The Call」にしみじみと心奪われた。ボブ・ディランとの親交でも知られるボブ・ニューワースが、1999年のアルバム『Havana Midnight』に収録していた曲で、旧友からの一本の電話で始まる切ない物語だ。ドイル・ブラムホールllのエレクトリック・ギターのソロも泣かせる。デレク&ザ・ドミノス時代からのブルースのスタンダード、「Nobody Knows You When Your'e Down And Out」は、殊に2000年代に入って彼のレパートリーの中でもすっかりお馴染みになった。この日も、客席からの手拍子が加わり、クリス・ステイントンのピアノも耳に残る快演だった。
考えてみれば、ブルースをロックの日常に引っ張り出し、こうやって満員の武道館で響かせるようにした最大の功労者はエリックだった。いまでこそ、当たり前のような光景だが、それが如何に大変で価値のあることだったか、改めて思う。そのためだけではもちろんないが、波乱万丈、彼の人生は激しい起伏とともにあった。若くして天才ぶりを騒がれ、大きな喜びもあれば、我々凡人には想像すらできない孤独や苦悩もあったはずだ。そのたびに、好むと好まざるにかかわらず、物語にはドラマティックな脚色が添えられてきた。それらを全て引き受け、背負いながらの人生だった。近年では、彼岸に渡っていく同世代の友人たちも少なくない。そうやって、いま80才だ。それなりの老いも感じさせた。そのせいかどうか、「Wonderfull Tonight」の歌いだしに間に合わず、慌ててマイクに歩み寄り、会場を微笑ましく和ませるようなこともあった。技術的にも、若い頃スローハンドと呼ばれた神業によどみがあったとしてもおかしくない。
それでも、「Badge」で始まり、「Old Love」、「Crossroads Blues」、「Little Queens Of Spades」といった後半のエレクトリック・セットでのギター・ソロは、圧巻だった。ドイル・ブラムホールllのギター、ティム・カーモンのオルガン、クリス・ステイントンのピアノ、各自がソロパートで存分に集中力を発揮し、リレーのバトンのように主役の座を手渡していく。それを楽しんでいたかにも見えていたエリックが、火がついたかのように加わってからのアンサンブルは、白熱したものへと一気に変わる。
いま持っている限りの技量と熱意で歌い、ギターを奏でた。そこには、スーパースターと呼ばれ、神ともまつられた人の傲慢さはひとかけらもなかった。それどころか、音楽に対して、自らの人生に対して謙虚なほどで、そしてなにより誠実に見えた。「Tears In Heaven」での、軽ろやかなテンポといい、爽やかなみずみずしさとは裏腹に、こみ上げてくる感情を押し戻すように、目を閉じながら歌うその表情が背後のスクリーンに映し出されたときは、エリック・クラプトンという人にほんの微かだが近づけるかのような気がしたくらいだった。もちろん、大きな錯覚に過ぎなかったのだけど。
背後のスクリーンと言えば、幾度となく彼がギターを弾く指の動きが大きく映しだされ、それに目を奪われ、見とれてしまうこともあった。弦を押さえたり、滑らせたりしながら動いていく指の所作がなんと美しくて柔らかく、優しくみえたことか。それは、優雅な舞いようでもあった。そんな彼を見ながら胸がいっぱいになり感じたのは、この人はまだまだ自分の中での大切なものを終わらせてはいない、旅の途中にいるのだということだった。学ぶことからも逃げず、戦うことからも退いてはいない。だからこそ、その力強い歌声にせよ、ギターの音色にせよ、生気が漲っていたのだ。穏やかに見えるが、生きることの怖さを知った人ならではの、生半可な激しさなどはいとも簡単に弾き返す円熟の強靭さが感じられた。ギターを抱えたそのたたずまいは、我々に励みさえもたらすような姿だった。ネイザン・イーストがベースのイントロで導く「Cocaine」で会場はこの日いちばんの盛り上がりをみせ、その余韻を残したままいったん引き下がる。そして、ボ・ディドリーの「Before You Accuse Me」で幕を閉じた。1974年10月の初来日から数えて51年、80才になった彼にとっての初めてのコンサートは、103回目の武道館でもあった。
文:天辰保文
写真:土居政則